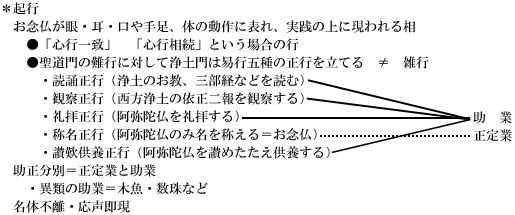
付録章◎ 帰敬式
帰敬式(承前)
(ⅲ)罪障懺悔
経に「一人一日のうちに八億四千の念あり、念々の中の所作、みな三途の業なり」とある。刹那刹那に罪を造って暮らしていることに気がつかず、まことにお恥ずかしいかぎりである。それらはすべて三途の業、つまりは地獄・餓鬼・畜生の三悪道に堕ちても不思議でないという凡夫の所業である。三途の川の正体は何かと言えば、貪・瞋・愚痴の三毒煩悩である。
皆人の 貪瞋愚痴の 悪水は
三途の川の 流れとぞなる
この三毒に、疑・慢・邪見を加えて六大煩悩。それに眼・耳・鼻・舌・身・意の六根が互いにからみ、過・現・未の三世にわたって果てることがないから「百八煩悩」になると言う。また身に三つ、口に四つ、意に三つの悪業を数えて合計「十悪」とも言う。
「懺悔偈」に「皆由無始貪瞋痴」といい、「従身語意之所生」というのがこれである。昨日入浴してサッパリ垢を落としても、また今日の垢がつくように、懺悔しても懺悔しても、三途の業を繰り返すばかりのわが身が恥ずかしいかぎりである。
これ程の ことは浮世の 習いぞと
心に許す 罪ぞおそろし
露ほどの 良きことあれば 誇り顔
悪しきは人に 知らせまじとて
悪水にドップリ浸かっていたら悪臭が分からなくなるように、浮世の常としてわれとわが身を許し、逆に少しばかりの善事でもあれば、人さまに宣伝したくなる、何とも困ったこの私である。
仏教ではまた「六道輪廻」と申して、先の三途(三悪道)に加えて修羅・人間・天上と、この六つの世界を流転するという、そんな自分の姿にまず気付かせていただくことが大切である。
人にこそ 包みながらも 省みて
うら恥ずかしき わが心かな
罪には「ツツミカクス=包み隠す」という意があると言われている。なるべく人さまに知られたくない、包んで隠してしまいたい程に恥ずかしい=ということは、罪を犯しながらも、どこかに良心があり、恥じる心があるから包み隠したくなるのであろう。しかしみ仏は何もかもお見通しである。そして自分の悪に気が付けば「懺悔せよ」と教えてくださっている。
自ら罪ありと知らば当に懺悔すべし
懺悔すれば即ち安楽なり。懺悔せざれば罪ますます深し
と。また、
罪ある者は懺悔せよ 懺悔すれば即ち清浄なり
とも説かれている。
懺悔とは梵語の「サンマ(音写して懺摩)」、漢訳して「
また「三障」といって業障・罪障・煩悩障の三つを断除したいと願うのも同様に懺悔の意である。
(ⅳ)本宗の本尊および祖師の恩徳
浄土宗では阿弥陀仏(阿弥陀如来とも言う)を本尊と仰ぎたてまつる。阿弥陀仏は法蔵菩薩と呼ばれたご修行の時代に「度・断・知・証」の総願のほかに「四十八願」という別願をお建てになり、殊に第十八願では、
「一切の衆生が、まこと心と疑いのない心、そして私が構えるであろう浄土に往生したいと願じて、南無阿弥陀仏とわが名を呼べば、十声にいたるまで必ず救い取るであろう」
と誓われ、その願を成就して阿弥陀仏とおなりくだされたのである。私たちはこの別願を〈本願〉とお呼びし、就中万機普益の第十八願を〈阿弥陀仏選択の本願〉といただくのである。万機普益とは、いかなる愚者・いかなる罪重の凡夫をも問わず、等しく救済せんとする阿弥陀仏大慈悲の働きである。月影があまねく水辺を尋ねて宿るがごとく、このお慈悲に洩れる衆生のない最勝・最易の道を選択くださったのである。経文を拝読すれば釈尊や諸仏もこの本願念仏を選択なされて濁世の灯とされたとある。また善導大師や宗祖法然上人もこの道を選択されて自らも救われ、後凡の私たちのために遺教されたのである。私たちは
インド・中国・日本と三国伝来の仏教のうち、浄土教の祖師と仰がれるお方はたくさんおられる。龍樹・天親・菩提流支・曇鸞・道綽・善導・懐感・少康・法然などの諸師である。いずれも浄土のみ教えを、身をもって実践し後世に伝えてくださった大徳である。これら数多くの祖師の中で、法然上人が、最も影響を受けられ、心から慕われたお方が善導大師であった。当ご本堂でも、皆さんのお家のお仏壇でも、阿弥陀さまの左、向かって右側にご安置申し上げているお方である。善導大師は唐時代初期に活躍された。最初には太原の近郊「玄中寺」でご修行になり、のちに長安の都に出られ、都の南にある秦嶺という巨大な山並みの一角、終南山の悟真寺に住せられ、時々は都に出て光明寺や実際寺でご布教されたようである。日常の
(Ⅴ)浄土宗の安心起行作業について
*安心
お念仏を申すについての「心の置きどころ・心の据えどころ」
一、総安心=厭離穢土 欣求浄土(娑婆を厭い離れて浄土を欣び求める心)
◎厭離穢土の心のみであれば → 纜(ともづな)を解きて漕がざる舟のごとし
◎欣求浄土の心のみであれば → 纜を解かずして舟を漕ぐがごとし
◎厭・欣の双(ふた)つが具(そな)わる=纜を解いて舟を漕ぐがごとし
二、別安心=至誠心・深心・回向発願心の三つの心
◎一心即三心 三心即一心=一心を離れて三心なく、三心を離れて一心なし
◎一心=南無=心存助給
◎一心=『小経』に依る。三心=『大経』や『観経』に依る。
・南無の心に嘘・偽りがない=至誠心
・必ず助けてくださると信じて疑わない=深心
・西方極楽浄土へ救っていただきたい=回向発願心
○至誠心=至とは真なり、誠とは実なり(善導大師)=真実心のこと
往生は 世に安すけれど みな人の
まことの心 なくてこそせね(法然上人)
真≠仮 実≠虚 虚仮の心を治す
・二祖対面=法然上人の真実心
○深心=深く信ずる心 → 信心を持って疑心を治す
「唯往生極楽の為には南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生するぞと思い取る」
・信機信法(機の深心・法の深心)
・「我たとえ死刑に行わるとも~」(法然上人)
○回向発願心=お浄土へとめぐらし向け、どうぞと願う心=不回向心を治す
「唯往生極楽の為には……」=極楽浄土へ往生したいという目標を確定する
「今まさに久近に修する所の善をして、めぐらして自他の安楽の因となすべし。諸々の衆生と共に無量寿国に往生せん」(善導大師)
・総回向(願以此功徳……)
・往相回向と還相回向
・ご先祖の回向
「父母を重くし思わん者は先ず阿弥陀如来に預け参らすべし」(法然上人)
「亡き人の追善には、その人の親族の者のつとむるぞ、必ずすみやかに届きはべるよし、お経には説かれたり」(福田行誡大僧正)
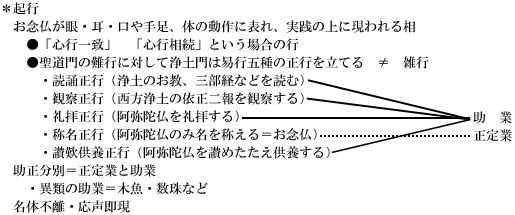
*作業
お念仏信者の守るべき生活態度
「念仏を勤むる振舞なり」(良忠上人『浄土大意鈔』)
◎恭敬修
慇重修とも名付く。驕慢心を治す
『西方要決』には次の五つを挙ぐ
・有縁の聖人を敬う
・有縁の像教を敬う
・有縁の善知識を敬う
・有縁の同伴を敬う
・広く三宝を敬う
◎無余修
雑起心を治す お念仏以外の余念余行なし
◎無間修
「念仏に
◎長時修
退転流動心を治す。
(ⅵ)三帰三竟の大意
※本書五八頁以下で詳述してあるので参照してください。
(ⅶ)五戒
※不殺生・不偸盗・不妄語・不邪淫・不飲酒の五つ=次の十重禁と重複するので、ここでは省略します。
(以下 次号)