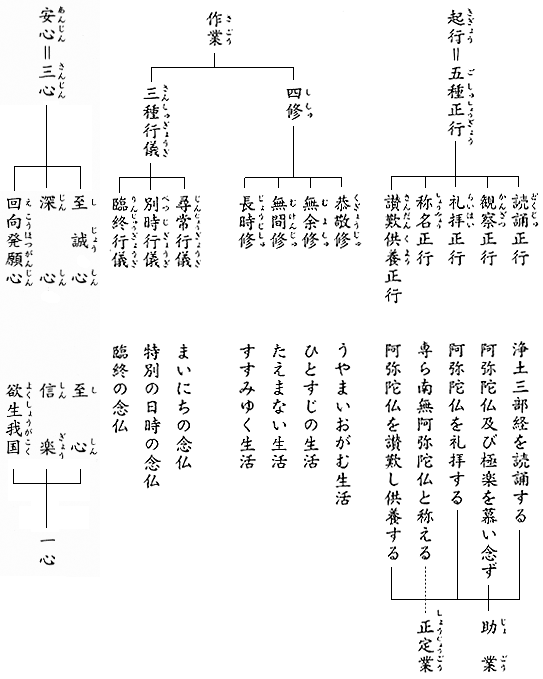
【資料L】
期 日 平成十年五月二日〜五日
伝燈師 龍徳山雲光院住職 服部光喜上人
勧誡師 大本山増上寺布教師 八木季生上人
| 五重相伝のしおり |
浄土宗東京教区江東組
五重相伝(ごじゅそうでん)とは
人として本当の生き甲斐に目覚める為に、念仏によりみ仏のみ生命をいただく道を五つ重ねにして伝えていただく作法。
五重相伝を受けると
仏の子が誕生する。そしてお念仏の実践者、念仏行者が育てられる。
五重相伝の成り立ち
前行の勧誡と正伝法に分かれる。
勧誡(かんかい)とは
正伝法に於て伝燈師から信仰の火を正しく受けられるように心構えをつくる。
正伝法(しょうでんぼう)とは
五重相伝の最終日に伝燈師から相伝を受ける。
五重(ごじゅう)の名目
初 重(しょじゅう) 往生記(おうじょうき) 元祖 法然上人作 【機(き)】
二 重(にじゅう) 授手印(じゅしゅいん) 二祖 聖光(しょうこう)上人作 【行(ぎょう)】
三 重(さんじゅう) 領解鈔(りょうげしょう) 三祖 良忠(りょうちゅう)上人作 【解(げ)】
四 重(しじゅう) 決答鈔(けっとうしょう) 三祖 良忠上人作 【証(しょう)】
第五重(だいごじゅう) [口授心伝](くじゅしんでん) 曇鸞(どんらん)大師作 【信s(しん)】
相 伝
三国八祖異途(いず)なく伝えられたもの
初 重 善導(ぜんどう)大師から法然上人へ
二 重 法然上人から聖光上人へ
三 重 聖光上人から良忠上人へ
四 重 良忠上人から当時の人々に残されたこと
第五重 インド・中国・日本と仏祖相伝のこと
三 国
インド 馬鳴(めみょう)・龍樹(りょうじゅ)・天親(てんじん)・菩提流支(ぼだいるし)
中 国 曇鸞・道綽(どうしゃく)・善導
日 本 法然
五重相伝の始まり
元祖法然上人滅後一八二年目、明徳四(一三九三)年、浄土宗第七祖・了誉聖冏(りょうよしょうげい)上人(伝通院開山)が、五十五個の伝目を定め、第八祖酉誉聖聡(ゆうよそうしょう)(増上寺開山)に伝えた。
化他(けた)五重(結縁(けちえん)五重)の始まり
徳川家康公の六代前の城主、松平親忠(ちかただ)公が、菩提寺の大樹寺開山・勢誉愚底(せいよぐてい)上人から、文明七(一四七五)年に受けたのが最初である。
■初 重 『往生記(おうじょうき)』 元祖法然上人 作
【機】この私のような至らぬものでも
―――自己を知り、己を深く反省することから信仰は始まる。
◎難遂往生機(なんすいおうじょうき)・・・・・・・・・・十三
*四障(ししょう)・・・・・・・・疑心(ぎしん)・懈怠(けだい)・自力(じりき)・高慢(こうまん)
*四機(しき)・・・・・・・・信心(しんじん)・精進(しょうじん)・他力(たりき)・卑下(ひげ)
◎種々念仏往生機・・・・・・・五
*愚鈍(ぐどん)念仏往生機――愚鈍の身になして
■二 重 『末代念仏授手印(まつだいねんぶつじゅしゅいん)』 二祖聖光上人 作
【行】南無阿弥陀仏と称うれば
―――如来様に救われるには、どういう行をすればよいか。
◎六重二十二件五十五箇の法数
安 心(あんじん)・・・・・・・・念仏申すについての心の持ち方
起 行(きぎょう)・・・・・・・・実践方法
作 業(さごう)・・・・・・・・安心起行の策励法
結帰一行三昧(けっきいちぎょうざんまい)・・・・・・奥図の伝・・・・・・ただ一向に念仏すべし
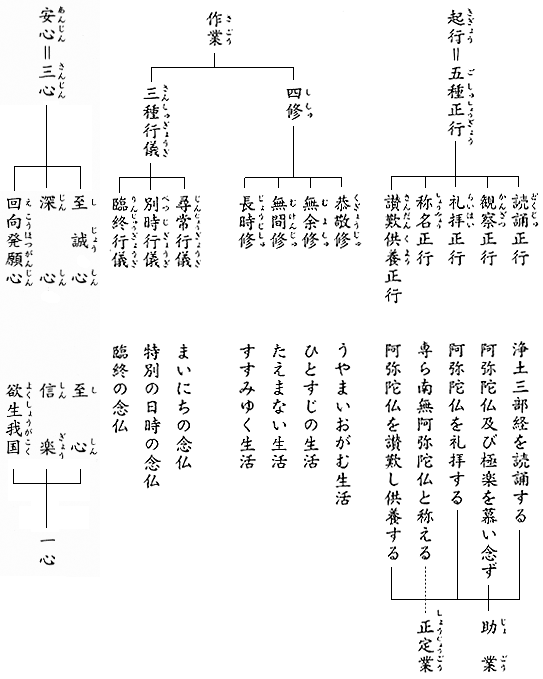
■三 重 『領解(りょうげ)末代念仏授手印鈔』 三祖良忠上人 作
【解】往生するぞと思いとり
―――念仏で救われることがはっきり了解された。
聞慧(もんね) 聞いてわかる・・・・・・・・仰信(こうしん) ・・・・・・・・知識
思慧(しえ) 考えてわかる・・・・・・・・解信(げしん) ・・・・・・・・知識
修慧(しゅうえ) 修行してわかる・・・・・・証信(しょうしん)・・・・・・・・智慧
■四 重 『決答授手印疑問鈔(けっとうじゅしゅいんぎもんしょう)』 三祖良忠上人 作
【証】一点の疑いなく
―――念仏生活の実際において起こる疑問の全てを払いのけ、信仰が自分のものとなった。
二河白道の比喩
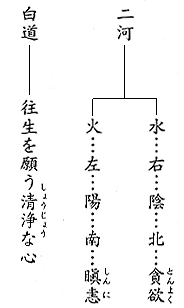
異学異見(いがくいけん) 別解別行(べつげべつぎょう)の声
南無阿弥陀仏ということは別したることに思うべからず。心に、阿弥陀仏、我を
助けたまえと思い、口に南無阿弥陀仏と称うれば、三心具足の念仏と申すなり。
■第五重 《口授心伝(くじゅしんでん)》 曇鸞大師 伝
【信】念仏相続の信仰に生きる
―――『観経』の「令声不絶具足十念称(りっしょうふぜつぐそくじゅうねんしょう)南無阿弥陀仏」を、曇鸞大師の『往生論註(おうじょうろんちゅう)』の十
念に寄せて伝える。
念仏と罪業(ざいごう)(業道は秤のごとし、重きものまずひく)
一、在 心(ざいしん)・・・・・・・・心について・・・・・・・・罪業…虚妄 倒(こもうてんとう)の心
念仏…真実無上の信心
二、在 縁(ざいえん)・・・・・・・・相手について・・・・・・罪業…煩悩虚妄の衆生
念仏…無漏清浄(むろしょじょう)の功徳
三、在決定(ざいけつじょう)・・・・・・・・時節の心理状態・・・・罪業…有後心(うごしん)
念仏…無後心(むごしん)
単信口称の勝方便(しょうほうべん)・・・・・・・・口授心伝
『ただ申す外に口伝も相伝も
なきが浄土の口伝相伝』
善導大師曰(のたまわ)く、仰ぎ願わくは一切の行者等、一心にただ仏語を信じて、身命(しんみょう)を顧みず決定して依行せよ。仏の捨てしめ給うものをば即ち捨て、仏の行ぜしめ給うものをば即ち行じ、仏の去らしめ給う処をば即ち去れ。これを仏教に随順し、仏意(ぶっち)に随順すと名づけ、これを仏願に随順すと名づけ、これを真の仏弟子と名づくなりと。(十念)
「ほんとうに生きんがために 今この食をいただきます
与えられたる天地の恵みを感謝いたします」
「月かげの いたらぬさとは なけれども ながむる人の 心にぞすむ」 法然上人