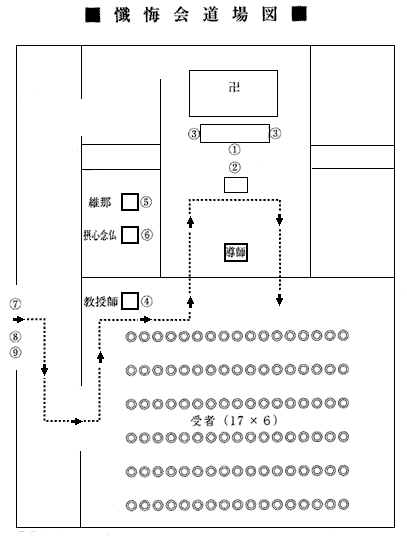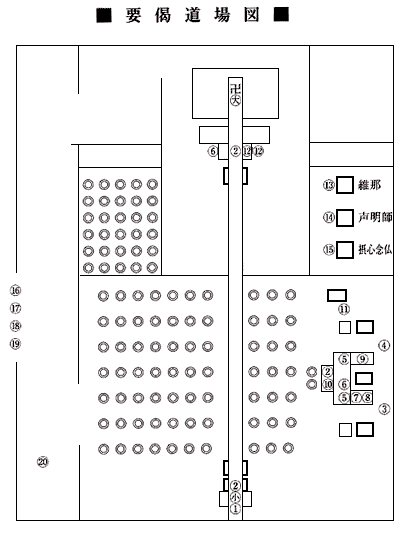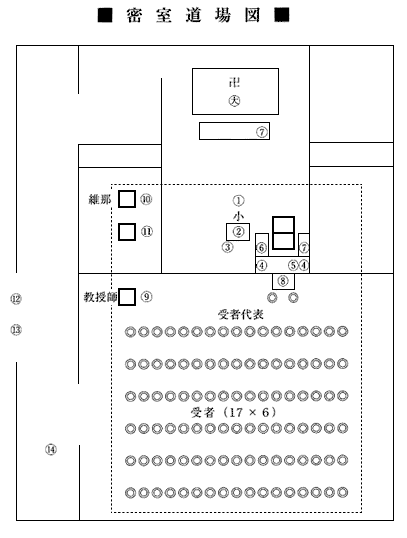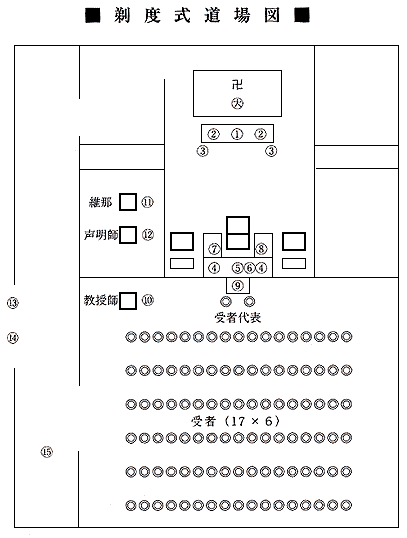【資料E】
五重相伝会講習会資料
江東組五重相伝会
日程:平成10年5月2日 5日
会場:東部 龍徳山 雲光院
〈1〉五重相伝会について
【伝法】法門を師から弟子へ伝授すること。(浄土宗大辞典より)
三代相承=『選択集』『一枚起請文』『授手印』『徹選択集』等の付嘱
了誉聖冏 書伝:三巻七書
口伝:五重五十五箇条・・・・・・・・五重伝法の始め
道誉貞把 五重八箇条、宗脈十一箇条
感誉存貞 五重九箇条、宗脈五箇条・・・・・・・・・・箇条伝法
【結縁五重=化他五重】大樹寺勢誉愚底から安城松平家初代親忠への五重相伝が始めとされる。現在の結縁五重は感誉流による要偈道場分九箇条、密室道場分五箇条、添口伝四箇条を相伝する。
【制度式】信者が在俗のまま、剃髪した出家と同様の思いをもって得度を受けることをいう。(同)
【懺悔会】五重相伝または授戒会において、その相伝を受けるに先だって、懺悔を行う軌式をいう。(同)
【要偈道場】伝法において肝要なを伝授する儀式を行う道場のこと。(中略)この要偈道場は正伝法前伝の道場であって、室内東方に釈尊の霊山浄土があり、西方には阿弥陀仏の極楽浄土がある。また、両浄土の間に自道があり、釈尊は東方にあって撥遣し、阿弥陀は西方から招喚される。この招きに従って行者は西に向かって往生する二河白道の様相を思念することを表している。(同)
【密室道場】五重相伝正伝法を行う道場のこと。道場を密室とし(中略)一座具の上に伝燈師ならびに受者が同座する(中略)。前伝の要偈道場 は穢土、この密室道場は往生浄土を表す父子相承の会座である。(同)
〈2〉五重相伝会中常備するもの
【本 堂】
〈本尊前〉香・華・灯明(朱蝋燭)・供物等
〈贈祭壇〉贈五重位牌・紅白鏡餅大・三具足・供物
【庫 裡】
〈勧誡室〉名号掛軸・紅白鏡餅小・三具足・木魚・割笏(引僧用)・調読帳
〈3〉道場の準備と要点
■ 剃 度 式 ■
【準 備】
◇内陣中央に外陣向きに高座を置き、その左右に脇師席を設ける。
◇高座前に受者代表席を設ける。
〈本尊前〉紅白鏡餅…大 ・ 父母尊位位牌…(1)
度牒・袈裟(受者全員分)…(2)
華籠(脇師四奉請散華用)…(3)
〈高 座〉燭台一対(朱蝋燭)…(4) 洒水器…(5)
水瓶…(6) 槌砧…(7)
度牒・袈裟・聖典・数珠(受者代表分)・剃刀…(8)
〈脇 師〉経机
〈受者代表〉経机・角香炉…(9)
〈教授師〉戒尺…(10)
〈維 那〉経机・大・小・戒尺…(11)
〈声明師〉経机・木魚(摂心念仏用)…(12)
〈道場入口〉塗香…(13) 触香…(14) 潅頂…(15)
〈和上控室〉柄香炉・香盒
説相箱(伝書・表白・請師文等)
※上記中、(1)、(2)などは次頁図中での位置を示す。
【要 点】
◇受者は浄衣を着けて入堂。
◇和上・脇師は(1)右脇師、(2)侍者(柄香炉)、(3)和上、(4)侍者(説相箱)、(5)左脇師の順に左後
門(外陣から向かって右側、以下同じ)から入堂。
◇表白の後、和上転向登高座、脇師もこれに合わせ転向着座。
◇和上開導作法の後、受者全員に剃度作法、(1)右脇師(水瓶)、(2)侍者(柄香炉)、(3)和上(剃
刀)、(4)左脇師(袈裟)、(5)侍者(袈裟持ち)の順に巡剃。
◇和上は摂益文・念仏一会を発声して下高座、本尊前に転向、脇師もこれに合わせ転向。
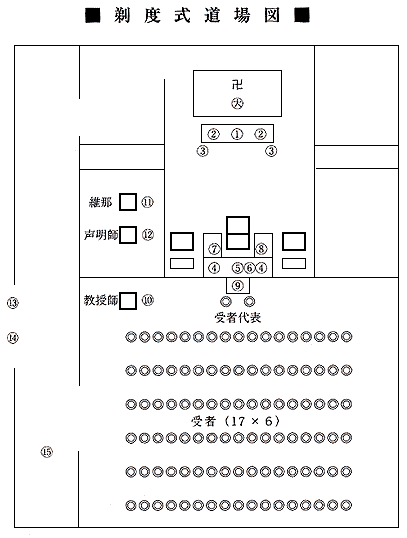
■ 懺 悔 会 ■
【準 備】
◇須弥壇と導師座の中間に浄焚用香炉、懺悔座を準備する。
〈本尊前〉火鉢(浄焚用)…(1)
三方…(2)
〈脇 師〉椅子…(3)
〈導 師〉礼盤
〈維 那〉経机・大・小・木魚…(5)
〈教授師〉戒尺…(4)
〈摂心念心〉…(6)
〈道場入口〉塗香…(7)
触香…(8)
潅頂…(9)
〈導師控室〉柄香炉・香盒
〈受者控室〉懺悔紙
〈その他〉照明具(広懺悔読誦用・階段通路用)
照明ウキ(六道僧用)
【要 点】
◇受者は浄衣を着けて入堂。
◇本尊用灯明1対のみ点灯、堂内は暗夜道場。
◇脇師は受者入室前に本尊前左右に着座。受者全員人堂後退堂。
◇受者は控室で懺悔紙に氏名を自署、これを持参して一人ずつ人堂。
六道僧の指示に従って懺悔座に着き焼香・座礼の後、懺悔紙を胸に当ててから三方上に
置き、所定の場所に着座。この間摂心念仏。
◇広懺悔捧読中に、懺悔紙を浄焚。
◇摂益文で点灯。
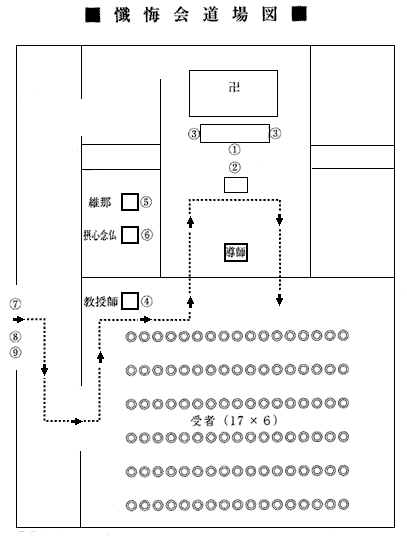
■ 要 偈 道 場 ■
【準 備】
◇外陣正面に釈迦三尊の掛け軸(1)を奉安し、本尊前から釈尊前まで細い白布を敷き、白道
を象る。
◇北側から白道向きに高座を置き、その前に受者代表席を設ける。
◇高座左右に脇師席を設ける。
◇高座後方に二河白道・二祖対面(四句偈)の掛け軸を掛ける。
〈本尊前〉紅白鏡餅…大 経机・香炉…(2)
洒水器(道場洒水用)…(6) 華籠(道場散華用)…(12)
華籠(伝灯師四奉請散華用)…(12)
〈釈尊前〉紅白鏡餅…小 経机・香炉…(2)
〈高 座〉燭台一対(朱蝋燭)…(5) 洒水器…(6) 水瓶…(7)
経巻…(8) 槌砧…(9)
〈高座後方〉二河白道・長散杖…(3) 二祖対面(四句偈)…(4)
〈脇 師〉経机
〈受者代表〉経机・角香炉…(2) 鉦…(10)
〈教授師〉戒尺…(11)
〈維 那〉経机・大・小・戒尺…(13)
〈声明師〉経机…(14)
〈摂心念仏〉経机・合…(15)
〈道場入口〉香水…(16) 香湯…(17) 塗香…(18) 触香…(19)
潅頂…(20)
〈伝燈師控室〉柄香炉・香盒
説相箱(伝書・要偈表白・授手印序・制誡・安心請決)
【要 点】
◇受者は浄衣を着けて入堂。白道をはさんで高座向きに並び、位置確定後本尊向きに着座。
◇伝燈師右繞三匝の後、侍者(柄香炉)先進で高座後方を通り釈尊前に至り、焼香・無言
三拝・敬礼偈・十念・無言一拝、白道を渡り本尊前者座。これに合わせて左後門から左脇
師、右後門から侍者(説相箱)、右脇師入堂。
◇表白の後、伝燈師は北側に転座登高座、脇師もこれに合わせ転座。
◇伝燈師は摂益文・念仏一会を発声して下高座、本尊前に転座、脇師もこれに合わせ転座。
◇受者は白道を渡り、潅頂(左脇師)、経巻伝授(右脇師)を受け退堂。
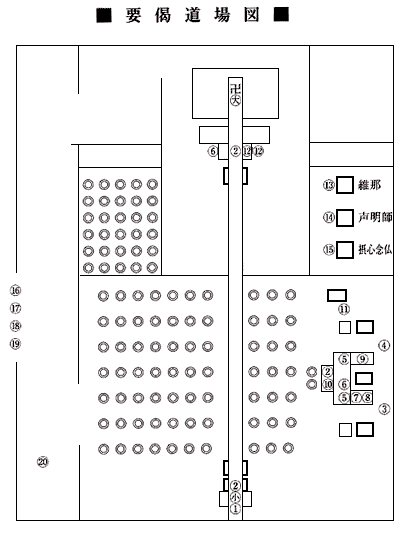
■ 密 室 道 場 ■
【準 備】
◇道場内は遮蔽し、全体に大座具を敷く。
◇内陣中央に伝法仏(1)を安置し、その左側(受者から見て右側)に外陣向きに高座を置く。
◇高座前に受者代表席を設ける。
◇大座具の上に散華を撒く。
〈本尊前〉紅白鏡餅…大 五重伝巻(受者全員分)…(7)
〈伝法仏前〉紅白鏡餅…小
三具足・供物…(2)
長散杖…(3)
〈高 座〉燭台一対(朱蝋燭)…(4)
洒水器…(5)
槌砧…(6)
五重伝巻(受者代表分)…(7)
〈受者代表〉経机・角香炉…(8)
〈教授師〉戒尺…(9)
〈維 那〉経机・大・小…(20)
〈摂心念仏〉木魚…(11)
〈道場入口〉塗香…(12)
触香…(13)
潅頂…(14)
〈伝燈師控室〉柄香炉・香盒
説相箱(伝書・伝巻見本)
【要 点】
◇伝燈師が先に入堂、本尊前・伝法仏前無言三拝の後登高座。
◇受者は浄衣を着けて入堂。
◇伝法仏を含め、伝燈師・受者等すべての人が大座具上に着座。
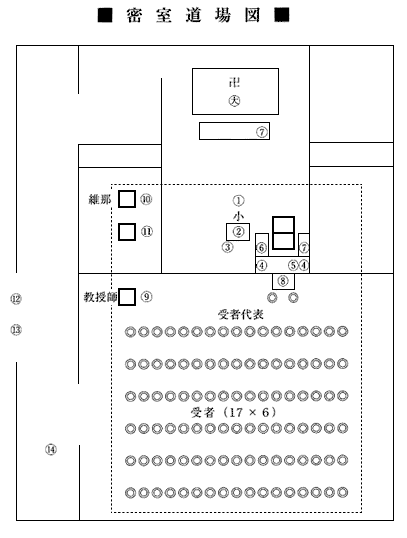
■ 晨 朝 ・ 日 中 ■
【準 備】
◇須弥壇前に未回向、贈祭壇前に回向済の贈五重巻物を奉安するための大三方を置く。
◇内陣中央に導師用経机と二畳台を置く。
〈本尊前〉大三方
〈導 師〉経机・二畳台・磬
〈維 那〉経机・大・小・木魚
〈式 衆〉経机(回向師を含む)
〈回向師〉三方・戒尺
〈受者係〉木魚・三方(各自)
〈道場入口〉塗香・触香
〈導師控室〉柄香炉・香盒
【要 点】
◇誦経・念仏は頭打ち。
◇受者係は受者の左右に適宜別れ、三方を持って待機。
◇導師式衆入退堂中は、係唱導で木魚念仏。
◇念仏一会中、侍者は本尊前の未回向贈五重巻物を回向師前へ レ動。
◇回向した贈五重巻物は三方に乗せ、適宜受者へ配布。
◇受者は巻物を一霊ずつ頂戴して、順に隣の受者へ手渡し。
◇回向済贈五重は、導師を経て贈祭壇前の大三方に奉安。